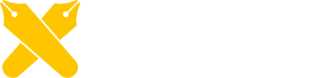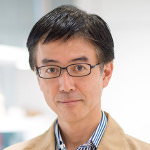SDM Voice|小木 哲朗教授(SDM教員)

メディアシステム研究室の代表として様々なメディアに関する研究を推進する小木哲朗教授。SDM研究科内の複数の教員や学生と共に推進する研究プロジェクトや、それらの取り組みによる実社会とのつながり、文系、理系の領域を超えたSDMの人材育成などについて伺いました。
Profile
小木 哲朗(おぎ てつろう)
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授
元・筑波大学 大学院システム情報工学研究科 准教授。専門分野:ヒューマンインタフェース、バーチャルリアリティ、臨場感コミュニケーション、ビジュアル・シミュレーション。著書に「サイバースペース入門」(日本実業出版社)、「シミュレーションの思想」(東京大学出版会)等がある。企業との協同研究
 私の研究室は、"メディアシステム研究室"という名前を付けています。ここでいうメディアとは、コンピューターをベースにした映像技術、例えば三次元CGやデジタルサイネージ、スマートフォンのようなデバイスなど、テキストと映像を使って表現できるもののことです。主な領域は、映像技術をネットワークにつなげたテレイマージョン(高臨場感通信)という、遠隔地に自分が没入して存在しているような感覚をいかに作れるか、あるいは遠隔地の人同士が没入感覚を共有してコミュニケーションを図れるようにするという研究分野です。具体的なプロジェクトの一つは、デジタルプラネタリウム環境の有効活用を目的とした、ドームの映像研究です。ドームに投影した映像は、3Dメガネをかけなくても立体的に感じる、空間の中に絵が動いているように感じるという特性があります。ここ1、2年は、その効果を上手く使いながら、三次元的な映像世界をどのくらい表現できるかということに取り組んでいます。
私の研究室は、"メディアシステム研究室"という名前を付けています。ここでいうメディアとは、コンピューターをベースにした映像技術、例えば三次元CGやデジタルサイネージ、スマートフォンのようなデバイスなど、テキストと映像を使って表現できるもののことです。主な領域は、映像技術をネットワークにつなげたテレイマージョン(高臨場感通信)という、遠隔地に自分が没入して存在しているような感覚をいかに作れるか、あるいは遠隔地の人同士が没入感覚を共有してコミュニケーションを図れるようにするという研究分野です。具体的なプロジェクトの一つは、デジタルプラネタリウム環境の有効活用を目的とした、ドームの映像研究です。ドームに投影した映像は、3Dメガネをかけなくても立体的に感じる、空間の中に絵が動いているように感じるという特性があります。ここ1、2年は、その効果を上手く使いながら、三次元的な映像世界をどのくらい表現できるかということに取り組んでいます。
その他には、NICT(情報通信研究機構)から予算が出ている、タニタさんと協同で進めている健康プロジェクトがあります。一般の方に加速度計を身につけてもらい、一日の運動量と消費カロリーを時間毎に記録します。その何十万人という人のライフログを分析して、健康管理に活用することを行っています。私がまとめ役をしていた、新潟県長岡市の"多世代健康まちづくり事業"の委員会で一緒だったタニタさんが、すでに"健康プログラム"というサービスを提供されていたこともあり、NICTのビッグデータ予算に合わせて、共同で何か提案してみましょうという話から実現しました。
文系、理系の領域を越えて
 授業では、情報系の"ネットワークとデータベース"や"シミュレーション技法"、"インターフェイス論"、"統計学"を担当しています。統計学は数学の一分野ですが、今は、文系だからといって数学を知らなくてもいい時代ではありません。ビッグデータをもとにシステムを考えていくには、最低限のデータの取り扱い方を学ぶ必要があります。SDMは、社会のニーズをしっかりと捉えて、そのニーズに応えられるシステムをデザインすることを目標としています。文系の学生であっても、自分の提案が社会でどのように役立つのかを考える必要はあり、例えば、アンケート調査の結果を分析して判断するのにも、統計学は重要だと考えています。
授業では、情報系の"ネットワークとデータベース"や"シミュレーション技法"、"インターフェイス論"、"統計学"を担当しています。統計学は数学の一分野ですが、今は、文系だからといって数学を知らなくてもいい時代ではありません。ビッグデータをもとにシステムを考えていくには、最低限のデータの取り扱い方を学ぶ必要があります。SDMは、社会のニーズをしっかりと捉えて、そのニーズに応えられるシステムをデザインすることを目標としています。文系の学生であっても、自分の提案が社会でどのように役立つのかを考える必要はあり、例えば、アンケート調査の結果を分析して判断するのにも、統計学は重要だと考えています。
授業以外では、国際提携を担当しています。SDMは設立当初から英語の授業を取り入れ、交換留学制度に積極的に取り組んできました。現在は、提携先大学で修得した単位が、こちらの学校の単位として認められ、SDMで納めた授業料で派遣先の授業を受けられるという提携を結んでいるのが6校、お互いに研究指導をし合うという提携先は10校あります。
マルチな視点を持った人材を育成

文系、理系にこだわらないのがSDMの特徴です。大学では一般的に、隣の先生の領域を侵してはならないという暗黙の了解があります。しかしこの研究科には、12人の専任教員が協力し合いながら、お互いの研究領域の間を埋めていくという文化があります。この点が他大学との大きな違いでしょう。設立時は、「SDMとは何か」という概念が固まっていませんでした。とにかく、アカデミックな世界に閉じこもっているのではなく、常に社会との関係を保つこと。自分の専門領域だけでなく、全体を俯瞰してみられる人材が必要だという共通認識のもとにスタートしました。私自身、研究は論文を書いて終わりにせず、その成果を実社会で試してみたという気持ちはいつも持っていて、様々な企業との協同研究もその思いが形になった一つです。教員同士が集まると様々な話題が飛び交い、ここに来てから政治の問題にも興味を持つようになりました。
SDMという環境にいると、マルチプレーヤー的な、いろいろな立場に立った視点を持つことができるようになると思います。これから、「今までのものを打ち壊して、新しい社会システムを作っていこう」という意欲を持ち、頭だけでなく地道に手足を動かして社会にアピールできる学生が増えるといいですね。今後、卒業生たちが社会でグループを作り、研究成果を実証していってくれることを願っています。