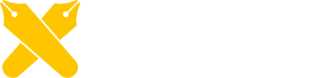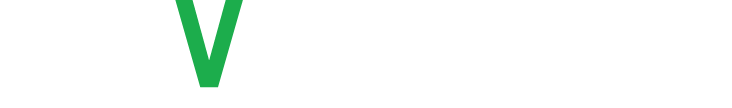SDM特別講義 2010年度 春学期
| 講義日程 | 講師・演題 |
|---|---|
| 第1回 2010年4月9日 モデレータ教員: 西村 |
 コマツ(株式会社小松製作所) 代表取締役会長 コマツ(株式会社小松製作所) 代表取締役会長坂根正弘 【演題】 コマツの経営構造改革 ~強みを磨き、弱みを改革~ ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール島根県出身。1963年大阪市立大学工学部卒業。同年コマツ(株式会社小松製作所)入社。89年取締役、90年小松ドレッサーカンパニー(現コマツアメリカ)社長、94年常務取締役、97年専務取締役、99年代表取締役副社長を経て2001年、代表取締役社長兼CEO就任。2007年より現職。 (社)日本経済団体連合会 評議員会副議長、環境安全委員会委員長、日本ロシア経済委員会副委員長。(財)日中経済協会副会長を務める。2003年、全国発明表彰 発明実施功績賞、08年、デミング賞本賞を受賞。 著書に『限りないダントツ経営への挑戦(増補版)』(日科技連出版)。 講義概要コマツは営業赤字に陥った2001年から、経営構造改革を推進。経営の「見える化」により、日本のモノづくりの強さを見極め、ダントツ商品の投入やアジアを中心とした海外事業の強化により強みを磨くとともに、固定費削減やガバナンス強化などの弱みを徹底改革。その成果として、業界のみならず、日本の製造業でもトップクラスの営業利益率を達成した。また、グローバルレベルでの更なる企業価値の向上を目指し、2006年にコマツウェイを明文化。トップ自らの実践と、ミドルアップ・ミドルダウンを通じて企業体質の強化を図っている。 本講義では、コマツの経営構造改革を通じて、コマツや日本企業、日本国家にとっての今後の課題を概説する。 |
| 第2回 2010年4月16日 モデレータ教員: 狼 |
 慶應義塾長 慶應義塾長清家篤 【演題】 生涯現役社会の条件 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール慶應義塾大学商学部教授、慶應義塾長。博士(商学)。専攻は労働経済学。 1978年、慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院商学研究科博士課程修了、同大学商学部助教授を経て、1992年より同教授。2007年より商学部長、2009年より慶應義塾塾長。この間ランド研究所研究員、経済企画庁経済研究所客員主任研究官等を歴任。現在、労働政策審議会委員(厚生労働省)などを兼務。近著に『エイジフリー社会を生きる』NTT出版(2006年)、『高齢者就業の経済学』(共著)日本経済新聞社(2004年、2005年の第48回日経・経済図書文化賞受賞)、『労働経済』東洋経済新報社(2002年)などがある。 講義概要慶應義塾大学商学部教授、慶應義塾長。博士(商学)。専攻は労働経済学。1978年、慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院商学研究科博士課程修了、同大学商学部助教授を経て、1992年より同教授。2007年より商学部長、2009年より慶應義塾塾長。この間、カリフォルニア大学客員研究員、ランド研究所研究員、日本労働研究機構特別研究員、経済企画庁経済研究所客員主任研究官等を歴任。現在、労働政策審議会委員・同労働力需給制度部会長・同雇用保険部会長(厚生労働省)、今後の高齢社会対策の在り方等に関する検討会座長(内閣府)、社会保障推進懇談会構成員(内閣官房)、公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会座長(人事院)などを兼務。主な著作に『エイジフリー社会を生きる』NTT出版(2006年)、『高齢者就業の経済学』(共著)日本経済新聞社(2004年、2005年の第48回日経・経済図書文化賞受賞)、『生涯現役社会をめざして』日本放送出版協会(2003年)、『勝者の代償』(訳)東洋経済新報社(2002年)、『労働経済』東洋経済新報社(2002年)、『生涯現役社会の条件』中公新書(1998年)、『人事と組織の経済学』(共訳)日本経済新聞社(1998年)、『高齢化社会の労働市場』東洋経済新報社(1993年、1994年の第17回労働関係図書優秀賞)、『高齢者の労働経済学』(1992年、1992年の義塾賞、1993年の沖永賞)日本経済新聞社、などがある。 |
| 第3回 2010年4月30日 モデレータ教員: 高野 |
 内閣府原子力委員会 原子力委員長代理 内閣府原子力委員会 原子力委員長代理鈴木達治郎 【演題】 テクノロジーアセスメント(技術の社会影響評価)の必要性と課題:原子力政策への示唆 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール東京大学工学部原子力工学科、マサチューセッツ工科大学技術と政策修士卒、工学博士。MIT研究員、(財)電力中央研究所研究参事などを経て、2010年1月より現職。 講義概要科学技術の進歩は、社会に予想しない影響(正・負)をもたらす。科学技術と社会の円滑な関係を構築するためには、科学技術の社会影響評価(テクノロジーアセスメント)を、社会制度として定着させていく必要がある。欧米にくらべ、日本での定着が遅れているテクノロジーアセスメントの必要性と課題を解説し、とくに原子力政策にとっての示唆について検討してみる。 |
| 第4回 2010年5月7日 モデレータ教員: 前野 |
 ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー 茂木健一郎 【演題】 脳と創造性 ■会場:日吉キャンパス独立館地下2階DB203号室 ■時間:16:20-20:30 講師プロフィール脳科学者 講義概要自己認識や、利他性など、現代社会において人間について考える上で重要ない くつかの問題について、システム脳科学の視点から考察します。 |
| 第5回 2010年5月21日 モデレータ教員: 高野 |
 東京電力株式会社 取締役副社長 電力流通本部長 東京電力株式会社 取締役副社長 電力流通本部長藤本孝 【演題】 エネルギーと地球温暖化問題 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール出身地:東京都 学歴:昭和45年3月 慶應義塾大学工学部卒業、 職歴:昭和45年4月 東京電力株式会社入社、平成元年7月 同社配電部地中配電課長、平成3年7月 埼玉支店営業部長、平成5年7月 配電部(副部長待遇)東京通信ネットワーク株式会社出向、平成7年7月 考査部副部長、平成8年6月 業務管理部副部長、平成9年6月 東京南支店世田谷支社長、平成11年9月 技術部光設備構築推進プロジェクトグループマネージャー(部長)、平成13年6月 配電部長、平成15年6月 取締役 情報通信事業部長、平成16年6月 常務取締役 新事業推進本部副本部長、平成18年6月 常務取締役 新事業推進本部長、平成19年6月 取締役副社長 電力流通本部長 講義概要我が国を取り巻く最新のエネルギー情勢と地球温暖化問題への対応について概説。最新の動向としてコペンハーゲンでの国際的な議論と産業界の考え方を紹介。我が国における具体的施策として特に電力会社と関わりの深い原子力、太陽光発電、ヒートポンプ、さらには昨今注目を集めているスマートグリッドの動向を示すとともに、低炭素社会実現のために電力会社が行っている取組みや考え方を解説。また、政権交代に伴う混沌とした情勢の中で明らかになりつつある現政権での政策動向と問題提起を行う。 |
| 第6回 2010年5月28日 モデレータ教員: 手嶋 |
 前政府代表・前外務事務次官、慶應義塾大学特別招聘教授、早稲田大学客員教授 前政府代表・前外務事務次官、慶應義塾大学特別招聘教授、早稲田大学客員教授谷内正太郎 【演題】 国家の本質を考える -外交の戦略と志- ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1944年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了後、1969年、外務省入省。在アメリカ日本大使館参事官、在ロス・アンジェルス日本領事館総領事、外務省条約局長、内閣官房副長官補などを経て2005年外務事務次官、2008年退官。事務次官として3年の任期を務め、「凛とした志の高い外交」を目指し、アジア外交の再構築の他、価値観外交、「自由と繁栄の弧」の基本方針などを策定し実行。現在は外務省顧問を務める傍ら、慶應義塾大学、早稲田大学、東京大学で教鞭を執っている。 著書「外交の戦略と志」(産経新聞出版)など。 講義概要時に人々を非常な運命に遭遇させる国家の本質とは何か。巨大な国家のシステムにあっては、外交と防衛はその両輪であり、経済は国の本体に内蔵されたエンジンである。そうした国家システムの運営を委ねられた者は、前後左右に目を配り、凛としてことに当たらなければならない。現代外交の視点から新たな国家のあり方を考える。 |
| 第7回 2010年6月4日 モデレータ教員: 前野 |
 SDM特別研究教授、日本アイ・ビー・エム株式会社 コンサルティング・サービス 戦略コンサルティング 執行役員 ヴァイス プレジデント SDM特別研究教授、日本アイ・ビー・エム株式会社 コンサルティング・サービス 戦略コンサルティング 執行役員 ヴァイス プレジデント金巻龍一 【演題】 ナレッジワーカーマネジメント ~IBMのサービスサイエンス実証実験結果~ ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール早稲田大学大学院 理工学研究科 博士前期課程修了、 日本ビクター、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)等を経て、プライスウォーターハウス コンサルタント(旧アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス)入社、 今年4月日本IBMと統合、現在に至る。専門領域は、企業統合マネジメント、プロフェッショナル人材管理、法人営業改革。主な著書は、「企業統合」、「カリスマの消えた夏」 講義概要従来の工業化社会でのビジネス成功要因は「不確実性の回避/管理」であり、そのため業務の高度標準化や定式化がさかんに行われました。 しかし、サービス社会での成功要因は従来とは大きく変わります。それは、いわば「不確実性を武器」とする経営です。 IBMでは、「未来企業の実験室」を標榜し、1990年からサービスサイエンス実証実験を行ってきました。異質なもの同士が集まり、それが知の化学反応を起こし、そしてイノベーションが生まれる、そのナレッジマネジメントの仕組みについて、事例を交えながらご紹介いたします。 |
| 第8回 2010年6月11日 モデレータ教員: 高野 |
 株式会社MUSB(ムスブ)代表取締役、クリエイティブ戦略家 株式会社MUSB(ムスブ)代表取締役、クリエイティブ戦略家関橋英作 【演題】 広告・マーケティングを救う、情緒価値をつくるブランディング ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール青森県八戸市生まれ。外資系広告代理店J・ウォルター・トンプソン・ジャパン(現JWT)に入社し、コピーライターから副社長までを歴任。その間、ハーゲンダッツ・アイスクリーム、英会話スクールNOVA、デビアス・ダイヤモンド、ネスレ・キットカットなど多くのブランドを育て、広告賞も多数受賞(ニューヨークADC賞、ACC賞、ギャラクシー賞、NYフィルムフェスティバル賞、クリオ賞など)。特にキットカットでは、いまや受験生のお守りになったキャンペーンを展開。クリエイティブ部門の責任者として、AME賞(アジア・マーケティング・イフェクティブ賞)グランプリを2年連続受賞するなど大成功を収めた。09年のカンヌ国際広告祭では、日本初となるメディア部門グランプリを、投函できるキットカット「キットメール」キャンペーンで受賞。現在、クリエイティブ・コンサルタント。ブランディングをする会社MUSB(ムスブ)の代表取締役&クリエイティブ戦略家として、主として企業のブランディングを手がける。そのほかに、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー、女子美術大学非常勤講師。広告マーケティング活動のほか、企業研修、各種セミナー、講演、執筆などを行っている。日経BPオンラインにて、コラム「マーケティング・ゼロ」を執筆中。著書に『ある日、ボスがガイジンになったら!?』-英語を習うよりコミュニケーションを学べー(阪急コミュニケーションズ)。「チームキットカットの、きっと勝つマーケティング」(ダイヤモンド社)。『通る企画書の、見せ方つくり方』(フォレスト出版)。「ブランド再生工場―間違いだらけのブランディングを正すー」(角川SSC新書)。「YESのスイッチ」~苦手な人にもウンと言わせる話し方108~(中経出版)。 公式ブログhttp://s-eisaku.jp/ 講義概要 |
| 第9回 2010年6月18日 モデレータ教員: 日比谷 |
 日野システック株式会社 代表取締役会長 日野システック株式会社 代表取締役会長日野正紀 【演題】 古文書に見る江戸時代の農村と現代農業再生への道標 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール学歴:1958年3月 慶應義塾大学工学部電気工学科卒 職歴:1958年4月 日野電業株式会社(現日野システック㈱)入社、1977年10月 代表取締役社長、2007年10月 代表取締役会長 現在に至る。 趣味:登山、スキー、古文書研究 講義概要江戸時代の農村の古文書を解読していると、世間の常識からいささか掛け離れた村の実態が見えてくる。一所懸命の土地から切り離された武士にとって、農村は一定の給料(年貢等)が入ってくる場所に過ぎない。独立を強いられた農村は時の有力者による将に懸命の努力で豊かさを享受していく。それは豊かさに魅せられ武士の身分を捨ててまで百姓になろうとする者が現れたほどである。農村は創意工夫を重ね額に汗する者が伸し上がりうる、が油断すればたちまち没落する活力に満ちた世界であった。そこには、現代の農村問題を解決する手掛かりがある。 |
| 第10回 2010年7月2日 モデレータ教員: 日比谷 |
 中外製薬株式会社 代表取締役社長 中外製薬株式会社 代表取締役社長永山治 【演題】 (仮題)激変する事業環境に対応する研究開発型製薬企業の新しいビジネスモデル ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール昭和22年4月21日生まれ 学歴:昭和46年3月 慶應義塾大学商学部卒業 職歴:昭和46年4月 株式会社日本長期信用銀行入行、昭和50年4月 ロンドン支店勤務、昭和53年11月同行退行、中外製薬株式会社入社、昭和58年2月 営業本部部長兼国際事業部部長、昭和60年2月 開発企画本部副本部長兼事業企画部長、昭和60年3月 取締役開発企画本部副本部長兼事業企画部長、昭和61年2月取締役薬専事業部副事業部長、昭和62年3月 常務取締役、平成元年3月 代表取締役副社長、平成4年9月 代表取締役社長(現任)、平成6年4月~平成7年度 東京大学経済学部非常勤講師「産業事情・医薬」担当、平成10年5月~平成16年5月 日本製薬工業協会会長、平成12年5 講義概要グローバルに激変する事業環境の中、求められる医療ニーズに応えるためのイノベーション創出に向けた中外製薬の取り組み事例(ロシュとの戦略的アライアンス、クロスファンクショナルな組織運営、産学連携)を紹介する。 |
| 第11回 2010年7月9日 モデレータ教員: 日比谷 |
 独立行政法人 国際農林水産業研究センター(JIRCAS) 理事 独立行政法人 国際農林水産業研究センター(JIRCAS) 理事安中正実 【演題】 世界の食料・環境問題に取り組むための研究システム ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール・昭和26年(1951)2月生。59歳。農学博士。 ・農林水産省農業工学研究所で、フィルダムの耐震設計、地震挙動に関する研究に従事。この業績で、科学技術庁長官賞研究功績者表彰等を受賞。 ・農林水産省において研究開発課長に就任。環境、食料等の研究プロジェクトおよびバイオマスニッポン総合戦略の作成に従事。総合科学技術会議の環境、ナノテク分野の研究方針策定に参画。 ・現在は、途上国における食料・農業・環境に関する国際共同研究をマネジメント。 講義概要現在、世界が直面している環境問題、食糧問題について概括し、世界および我が国における研究の組み立ての考え方を紹介する。また、海外での研究協力を事例として、自然科学、社会科学の様々な要素が含まれる問題についての研究システム、およびそのマネジメントについて紹介する。 |
| 第12回 2010年7月16日 モデレータ教員: 林 |
 キャスター・慶應義塾大学大学院SDM研究科特別研究教授 キャスター・慶應義塾大学大学院SDM研究科特別研究教授林美香子 【演題】 農都共生のススメ ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール札幌生まれ。 北海道大学農学部卒業後、札幌テレビ放送株式会社にアナウンサーとして入社。 退社後、フリーに。現在は、エフエム北海道「ミカコマガジン」出演の他、執筆活動も。 「食」「農業」「環境」「地域づくり」などのフォーラムにパネリスト・コーディネーターとしても参加。 「農村と都市の共生による地域再生」の研究で北海道大学大学院にて、博士(工学)・Ph.Dを取得。 2008年4月から慶應義塾大学大学院SDM研究科教授。 著書に「農村へ出かけよう」(寿郎社)など多数。札幌在住。 講義概要地域再生が急務と言われる現代の日本。 地域再生を実現するひとつの方策として「農都共生=農村と都市の共生」をテーマにし、 農都共生の考え方、国内、海外の先進的事例などを紹介する。 農都共生ラボやアグリゼミの活動についても、紹介する。 |
| 第13回 2010年7月23日 モデレータ教員: 高野 |
 社団法人日本原子力産業協会 参事 社団法人日本原子力産業協会 参事北村俊郎 【演題】 原子力の安全と技術者の倫理 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1967年 慶應義塾大学経済学部卒業、日本原子力発電(株)入社。本社、東海発電所、敦賀発電所、福井事務所に勤務。理事社長室長、直営化推進プロジェクトチームリーダーを歴任。現在は日本原子力産業協会に勤務。主に労働安全、社員教育、地域対応、人事管理、直営工事などに携わり、数多くの現場経験をした。原子力発電所の安全管理や人材育成についてIAEA、ICONEなどで発表。 講義概要現代社会では分業が進み、技術が専門化している。技術者は一般の人からその専門分野の技術の扱いを任されているが、もし技術者が信頼を損なうようなことをすれば、社会が成り立つ基盤が崩壊しかねない。原子力産業においては過去にはチェルノブイリ事故があり、国内においてもJCOの被ばく 事故があった。数年前には原子力発電所における一連の事故隠し、データ改ざんなどの不祥事があり、以来、関係者は事故防止、不正防止に懸命に 取り組んでいる。一般にはあまり知られていない原子力の現場はどのような体制や運用となっているかについて海外の事例も含め解説し、こうした事故や不正は何故 起きるのか、どうしたらなくせるのか、そのためにすべきことは何なのかについて持論を述べる。さらにこれからの企業経営において、経営層、管理層、従業員がどのような価値観、倫理観を持って取り組むべきかについて、これまでの経験から得られた教訓などについて述べる。 |
| 第14回 2010年7月30日 モデレータ教員: 日比谷 |
 タカタ(株) ワシントン事務所長 Senior Vice President タカタ(株) ワシントン事務所長 Senior Vice President樋口和雄 【演題】 自動車安全について ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1968~1971年 慶應義塾大学、佐藤(武)研究室で車の衝突安全の研究‐‐‐日本で最初に衝突時の乗員の挙動のコンピュータs-シミュレーションをやった世代です。 1971年 慶應義塾大学工学研究科機械科修士課程終了 1971年 本田技術研究所入社 同じく車の衝突安全の研究、ESV(Experimental Safety Vehicle)の開発、オートマチックシートベルト、シートベルトプリテンショナー、エアバッグ、側面衝突対策、歩行者保護などの研究開発に携わる。 1992年 Honda Washington事務所赴任 米国運輸省に対するTechnical Representative 2000年 タカタ入社 ワシントン事務所設立 対米国運輸省代表、各種技術連絡、共同研究、委託研究のCoordinator 講義概要・交通事故の統計的概要 ・車両安全法規が出来るプロセス ・安全研究(研究ツール(ダミー)、人間の耐性、Biomechanics、実験) |