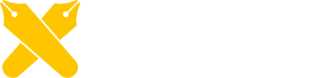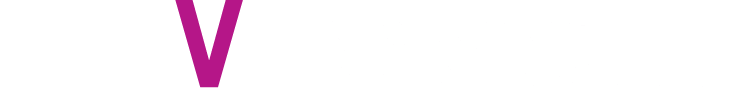留学プログラム
交換留学 派遣プログラムについて
 システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科には、研究科独自の交換留学制度があります。
システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科には、研究科独自の交換留学制度があります。
<単位互換協定のある交換留学>
1. デルフト工科大学、技術・政策・管理学部(オランダ)
2. ミラノ工科大学、経営工学プログラム(イタリア)
3. 国立応用科学院トゥールーズ校(INSA Toulouse)(フランス)
4. チュラロンコン大学、工学部(タイ)
<訪問研究者としての交換留学>
5. パデュー大学、工学部、パデュー・ポリテクニク・インスティトゥート(米国)
6. マサチューセッツ工科大学 (MIT)、複合工学システムセンター(米国)
7. カーネギーメロン大学、ハインツカレッジ(情報システム・公共政策)(米国)
8. スイス連邦工科大学(ETH Zurich)(スイス)
その他 ケンブリッジ大学(注2)、アジア・中東学部(英国)
訪問研究者として留学する場合は、SDM の学生は訪問中に研究活動/プロジェクトを行うため、授業を受けることはできません (単位は取得できません)。
これらの協定校で取得した単位は、SDM研究科委員会の承認により、学則に定められた範囲内で修了に必要な単位として認定されることがあります。派遣生は留学中慶應義塾大学に授業料を納入し、派遣先大学での授業料は免除されます。
 |
デルフト工科大学技術・政策・管理学科(オランダ) Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology (TU Delft), The Netherlands |
|---|---|
 |
ミラノ工科大学管理・経済・産業工学科(イタリア) Department of Management, Economics and Industrial Engineering, Politechnic University of Milan (Polimi), Italy |
 |
国立応用科学院トゥールーズ校(フランス) National Institute of Applied Science Toulouse (INSA Toulouse), France |
 |
チュラロンコン大学(タイ) Chulalongkorn University |
 |
パデュー大学工学部(アメリカ) College of Engineering, Purdue Univeristy, USA パデュー大学(パデューポリテクニクインスティトゥート)(アメリカ) Purdue Polytechnic Institute |
 |
マサチューセッツ工科大学(アメリカ) Engineering Systems Division, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA |
| カーネギーメロン大学、ハインツカレッジ(情報システム・公共政策)(米国) Heinz College of Information Systems and Public Policy, Carnegie Mellon University |
|
 |
スイス連邦工科大学(ETH IVT)(スイス) Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) |
慶應義塾大学 海外協定校一覧
青井奨学会でのケンブリッジ大学への留学プログラム
派遣学生の声
<2024年度>
報告1【デルフト工科大学】
2024年秋より半年間、オランダのデルフト工科大学にて交換留学を経験した。デルフト工科大学の修士課程は学士の延長としての位置づけが強く、講義においてはインプット量とディスカッションの多さが印象的であった。どの講義も非常にインタラクティブであり、自ら考え、意見を持ち、議論する学生の姿勢には日本の教育環境との大きな違いを実感した。また、デルフト工科大学はアントレプレナー教育や起業支援にも力を入れており、学習からR&D、ビジネス化までの流れが体系化されている点も特筆に値する。私自身も起業プロジェクトを行う講義を受講し、熱意あふれる学生や起業家たちに囲まれながら自身のキャリアや社会貢献について再考する有意義な機会となった。正直なところ、どの講義でも言語の壁やハイレベルな内容には苦労したが、世界最高峰の教育環境の中で自身を試し続けた経験は何物にも代え難い貴重な財産となった。また、約半数を海外学生が占めるデルフト工科大学の修士課程では毎日が国際交流の連続であり、異なる文化背景を持つ学生との交流を通じて凝り固まった自分の価値観を壊し、再構築できたように思う。現地で知り合った日本人学生と共同で企画した「Japanese Party」をはじめ、様々な場面で日本文化を発信するなかで自国に対する見方や感情が次第に変化した感覚もある。加えて、ヨーロッパでは近隣国へ気軽に訪れることが可能であり、私も留学プログラムの空き日程を活用して十数カ国を旅することができた。留学期間の大半を過ごしたオランダだけでなく、多くの国の文化や生活に深く踏み込み、各国特有の空気感や人々と触れ合うことができたのは非常に貴重な経験だった。無事帰国したいま振り返ると、自分にとって留学は色々な意味で人生最大の投資であり挑戦であったが、その見返りはその投資額を大きく上回るものになった。しかしここで満足するのではなく、この期間で得た貴重な経験や人間関係を糧にさらに人生をダイナミックに飛躍させていきたい。

報告2【ミラノ工科大学】
2024年9月から2025年2月まで、イタリアのミラノ工科大学で交換留学を経験しました。ミラノ工科大学はイタリア国内屈指の名門校であり、ヨーロッパ各国から多くの学生が集まる国際色豊かな環境が魅力です。私はこの恵まれた環境の中で、授業だけでなく日常生活においても積極的に人との交流を深め、自分の世界を広げることに努めました。留学中は Management Engineering という研究科に所属し、3つの授業を履修しました。その中でも High-end and Luxury Industrial Management では、ラグジュアリー業界の戦略やサプライチェーンについて学びました。この授業では、PRADAやGUCCIといった世界的ブランドのゲストスピーカーとのディスカッションの機会もあり、ミラノという土地ならではの魅力を実感することができました。留学当初は、4時間続く授業や英語でのディスカッションに慣れるのに苦労し、時には気が滅入ることもありました。しかし、素晴らしい友人たちに恵まれ、集中力が切れたときには一緒にエスプレッソを飲みに行ったり、卓球をしたりすることで、次第に現地のキャンパスライフに馴染んでいきました。特にディスカッションでは、英語を母語としないメンバー同士だからこそ、意見の食い違いや誤解を防ぐために、「何に納得したのか」「今何を考えているのか」を積極的に確認しながら進めることを意識しました。また、授業以外の活動にも積極的に参加しました。学生団体のイベントに足を運んだり、ミラノ工科大学に通う日本人コミュニティにも顔を出したりすることで、人とのつながりを広げることができました。イタリアでの生活では、英語が通じにくい場面があったり、建物が古いため毎月のように何かが壊れたりと、思いがけないトラブルにも遭遇しました。しかし、その一方で、歴史や文化の奥深さ、美しい自然、そして何よりも食事やお酒の美味しさなど、そうした困難を超えて余りある魅力に満ちた国でもありました。この半年間の留学は、間違いなく私の将来に大きな影響を与える貴重な経験となりました。これから交換留学を考えている皆さんにも、ぜひこの経験を通じて多くの学びや気づきを得ていただければと思います。

報告3【ケンブリッジ大学】
私は、2024年12月より2025年1月にかけて、青井奨学会青井交換留学奨学金賞の支援を得て、英国ケンブリッジ大学へ留学し、アジア・中東学部に在籍しながら約1ヶ月の間、自身の修士研究に取り組みました。短期間の留学でしたが、大学図書館や各研究科の図書館において多くの関連文献や先行研究に触れながら、研究者へのインタビューや論文の執筆を進めることができ、有用な時間を過ごすことができました。また、ケンブリッジ大学内の日本人コミュニティに参加する機会をいただき、日本では決して出会うことのないであろう幅広い分野の専門家や学生の皆様と交流する機会を得ることができました。12月のケンブリッジは、曇天が多く、日本と同様に冷え込みの厳しい時期でしたが、クリスマスや年末年始のシーズンの街の彩りは素晴らしく、日本とは異なる文化的空間を体験することができました。また、ケンブリッジ大学の歴史ある校舎や伝統ある街並みに直接触れることができたことは、留学を通じて得た学術的な経験と同様に自身の人生にとってポジティブな影響を与えてくれたと考えています。本留学を通じて得た、視点や考え方を自身の修士研究に留めることなく、今後のキャリアにおいても活かし、自身の研究成果や仕事におけるアウトプットに存分に援用していきたいと思います。最後に、本留学をご支援くださいました青井奨学会の皆様に今一度感謝申し上げます。

<2023年度>
報告1【デルフト工科大学】
私はデルフト工科大学に1年間の交換留学を経験しました。留学の前半6か月は通常の授業を受講しました。交換留学生には必修科目がなく、自分の興味に応じて自由に授業を選択できるのが魅力でした。私は特に少人数制でディスカッションを重視する授業を好んで履修し、他の学生たちと意見を交わしながら授業を受けたり課題に取り組むことを楽しみました。留学後半の6か月間は授業は受けずに Dual Certification Program に参加することにしました。これは慶應義塾大学とデルフト工科大学の両方の指導を受けながら修士研究を進めることができる研究プログラムです。興味のある研究領域で活躍されているデルフト工科大学の研究者に直接アプローチし、スーパーバイザーとして指導を受けながら、オランダとイギリスで現地調査を実施しました。さらに、国際学会へ論文を応募する経験を得ることができ、多くの学びを得ました。学校以外の研究活動としては、イギリスやドイツなど研究機関が多い国へ遠征し関心のある学術分野のワークショップや学会に参加したり、気になる研究に関わっている研究者を訪問したり、ヨーロッパ圏内にいることを利用してデルフト工科大学だけではない交流もすることができました。学術関係以外の交流機会を増やすためにスタートアップが集まるシェアオフィスに所属し、ビジネスパーソンとの交流も心掛けました。さまざまな交流をする中で、自分の研究領域に関連したワークショップを現地のスタートアップ向けに主催したり、領域横断した学術コミュニティで発表するなど発信の機会を見つけることができたのは、学生期間にしか得られない貴重な経験になりました。
フルタイムで仕事をしているとなかなか得られない自由な時間と多様な環境での生活で得た経験は、新たなキャリアを今後築いていく上で大きな糧になりました。この度は貴重な機会をありがとうございました。

報告2【ミラノ工科大学】
2024年2月から7月の半年間、ミラノ工科大学のManagement Engineeringコースで交換留学を経験しました。私はSDMの最終学期に留学し、留学期間内に修士研究を完成させる必要があったため、現地ではSDMでは開講されていない分野であり、かつ自身の仕事にも関連のある「Policy Design and Evaluation」と「New Forms of Organization」、さらにオプショナルのイタリア語講義のみを履修しました。授業は1コマ4時間と長く、日本の講義と比べても集中力が求められました。また、グループワーク中心であったため予習を入念に行わなければ議論についていけない状態でしたが、優秀なメンバーたちとの協働を通じて多くの刺激を受け、乗り越えることができました。課外活動では、ミラノ工科大学の音楽団体に加入し、オーケストラでフルートを演奏する機会を得ました。現地のイタリア人中心のコミュニティに加わったことで、講義だけでは得られないリアルなイタリアの文化を体験できたほか、他学科の学生や卒業生とも交流を深めることができ、とても充実した時間を過ごすことができました。私はこれまで本格的な留学経験がなく、また英語も得意ではなかったため、不安も少なからずありました。しかし、一歩踏み出してみることで語学力の向上はもちろん、これまで意識していなかった自身の価値観に気づくことができ、今後の人生について深く考える貴重な機会となりました。海外留学に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひSDMのネットワークを活用し、積極的に異なる環境に挑戦されてはいかがでしょうか。特にミラノは、料理やお酒が美味しいだけでなく、ミラノ・サローネやファッションウィークをはじめとするイベントが定期的に開催されるなど、暮らしていてとても楽しい街です。留学中には困難に直面することもあるかもしれませんが、それを上回る素晴らしい出会いや経験を通じて、他では得難い財産を手にすることができるはずです。

報告3【チュラロンコン大学】
2024年1月から2024年4月までタイ・チュラロンコン大学に留学しました。
留学先での活動について、月曜日〜金曜日の10時〜16時半はワーキングタイムに指定されており、自分のデスクで他の学生との意見交換やフィールドワーク、オープンデータを活用した情報の可視化を研究活動の主として行っていました。現地でのフィールドワークでは、洪水が発生する際の環境要因や背景、洪水による感電などの二次災害のリスクを把握することを目的としてチャオプラヤ川周辺地域における市民の生活環境や歴史の調査、排水設備の視察、電線整備の現状視察を主として行ないました。具体的な活動内容としては、河川周辺地域の視察による市民の生活環境の状況の把握、バンランプー博物館を訪問による河川周辺地域における生活様式の変化の理解、河川周辺地域の排水設備を視察し水位監視設備やごみ問題の知見の蓄積、電線整備の視察による二次災害リスクの高い地域の把握をすることができました。課外活動動としては、タイの政府機関の1つであるNational Research Council of Thailand (NRCT)の主催で行われた、東南アジア最大級の小中学生に研究に関心を持ってもらうためのイベント "Inventors day" において、自身の研究のベースとなる準天頂衛星みちびきの災危通報システムの仕組みと所属する神武研究室でのみちびきに関する関連研究の紹介を5日間に渡りプレゼンさせていただきました。この活動から英語でのプレゼン能力の向上や自身の研究への理解をさらに深める事ができました。

<2022年度>
報告1【デルフト工科大学】
私は修士1年の秋学期をオランダのデルフト工科大学で過ごしました。留学中はデルフト工科大学TPM研究科、CoSEMコースに在籍していました。もともと自分の興味ある分野の授業に加え、国内では本格的に学べる機会の少ない授業や、他の研究科の授業も受けるなど、自分の視野を広げるよう努めました。学期のはじめは英語でのディスカッションに慣れていないこともあり授業についていくのも精一杯でしたが、いずれの授業担当の先生方、学生方にも快く迎えていただき、最終的には現地のスタイルに馴染むことができました。異なる文化や考え方をもつ学生が世界中から集まり交じり合う環境で、学び、ディスカッションし、課題に共同で取り組めたのは計り知れない財産になったと思います。特に、デルフト工科大学の授業を機会として、修士研究の核となるアイディアに出会えたのはSDM生活の中でも特筆すべき経験でした。様々な刺激を浴びたおかげもあり、留学後には自分の物事の見方が変わったとはっきり実感できました。具体的には、相手の意見と自分の意見が対立している場合でも、意見の中で共通しているポイントを探し、自分の視点を変えて相手の見方に近づけることを意識するようになりました。海外留学は自分にとってはじめての経験で、異なる文化圏で生活のリズムを築くのに苦労しました。環境に慣れ始めてからは、学外でも人とのつながりを作ることに挑戦し、現地のレクリエーションコミュニティにも定期的に参加していました。クリスマスシーズンにはコミュニティのメンバーからホームパーティに誘っていただき、オランダの家庭料理・伝統料理を振舞っていただきました。鮮やかな色合いのエルテンスープや、具材満点のスタンポットの味は一生忘れないでしょう。SDMにご入学された皆様には、ぜひ海外留学の機会を活かし、新たな世界と学問の探求に挑戦していただきたいと思います。

報告2【ミラノ工科大学】
2022年9月から2023年2月末まで、イタリアのミラノ工科大学で交換留学を経験しました。ミラノ工科大学は、ミラノに本部を置くイタリアの国立大学であり、QS世界ランキングでは、建築学部は世界7位など、国際的にも知名度があり、毎年多くの学生が世界中から集まります。私が所属した研究科はManagement Engineeringで、Design Thinking for Business、Strategic Innovation、Vision and Change、Collaborative Sustainability Impact for Innovationの4つの授業を履修し単位を取得しました。イタリアの授業は、4時間通しで実施され、自由にコーヒーブレイクなどを取って良いことアクティビティメインで授業が行われることは、とても新鮮でした。4つの授業の中でも、特にDesign Thinking for Businessクラスには思い入れがあり、この授業ではデザイン思考(意味のあるイノベーション理論)で有名なミラノ工科大学所属のロベルト・ベルガンティ先生のフレームワークなどを利用し、イタリアの企業と連携しながら、イノベーティブな解を生み出すことを経験することができました。また、ミラノ工科大学での試験勉強は、マークシート/記述試験→合格した場合 口頭試験があり、何百ページもある授業の資料を暗記、理解することはとても過酷であったことも今となっては良い思い出です。イタリアは、街が美しいこと、食べ物・お酒が美味しいことなどあり、充実した日々を過ごすことができました。一方で、イタリアの建物が全体的に古いこと、各種手続きに時間がかかること、コミュニケーション部分で苦労した点もありますが、日本とは全く異なる社会で生活できたことで、自分自身を成長させることができました。

報告3【コペンハーゲン大学】
2023年2月から6月まで、デンマークのコペンハーゲン大学に留学をした。留学中、デンマークにおけるウェルビーイングやスタートアップエコシステムの現状について研究を進めた。デンマークの国土は日本の九州と同じくらいの面積で、人口は600万人弱でありながら、幸福度、格差の小ささ、汚職の低さ、デジタル競争力、国際競走力などのランキングで常に上位の国となっている。なぜ小国であるデンマークが国際社会で存在感を発揮できるのかを理解するために、まずは、デンマークの社会や文化、歴史を体系的に学習できる講義を受講した。また、デンマークの人たちが持っている価値観を知るために、語学面での不安はあったが、事前に質問を準備しながら、様々なデンマーク人と積極的に交流することを心がけた。そして、自分から主体的に働きかけることで、日本文化を教えているデンマーク人の教授のクラスに参加して、日本とデンマークのウェルビーイングについて発表をする機会なども得た。加えて、大学のイノベーションハブが主催の起業プログラムである「UCPH Lighthouse Lead-In Student Entrepreneurship Program」に参加し、自分の起業アイデアを育てていく経験をした。デンマークの人々がどのような形で、プロジェクトやビジネスを前進させていくのか、イノベーションを創出するための工夫、仕組みについて、日本との相違点を意識しながら学ぶことができた。留学を通じて、デンマークの人々は、社会全体の信頼をベースとして、他者を尊重しながら、自分の意見を率直に伝えるコミュニケーションができており、人々は互いにオープンで穏やかで、失敗に対して寛容な文化があると感じた。デンマークには「PYT(ピュット)」という言葉がある。これは、何かネガティブな出来事が生じた時に、「まあいいか」「なんとかなる」と気分を切り替えるために人々が言う言葉である。デンマークの人々が幸せにビジネスに挑戦し続けることで、成果を出しているカギがこの心の状態にあると思う。私自身も、デンマークで学んだPYTの精神を大切にしながら、今後もしなやかに挑戦を続けていきたい。

報告4【ケンブリッジ大学】
2023年12月に1ヶ月間、青井奨学金(Aoi Global Research Award)を受領し、イギリスケンブリッジ大学に留学をしました。本留学は、研究留学であるため、授業は履修せず、自身の修士研究に関係のある先生方にインタビュー、図書館などの施設を利用させていただきました。インタビューは、自身の修士研究が「日本の中、高、大学生の知的リスクを取る意欲向上を促す手法の開発」であっため、現地ではSDMの学びに近い研究をされている工学部の先生、Creative Educationを専門とする教育学部の先生、リスクを専門とするUniversity Center for Risk Studiesの教授にお時間を頂戴し、研究に対するアドバイスをいただきました。初めてお会いしたのにも関わらず、熱心に研究に対し、視座を共有してくださり、日本だけに留まらず、海外で自分の研究や思いを発信していくことの重要性に気づきました。イギリスの12月は、とても寒く、毎日天気も雨だったのですが、ケンブリッジの美しい街並み、芝生の青々しさ、交通機関も通常に動いていることなど、快適に留学生活を過ごすことができました。

海外留学に興味を持っている方へ
- 海外留学情報
- 海外留学のための奨学金情報
- 国際センター主催「学内の国際交流」
国際センターでは、外国および日本の文化や社会、国際関係を理解するための英語による講座を開講しています。
国際研究講座で取り扱う国/地域は、アジア・オセアニア、北米、ヨーロッパからアフリカにおよぶほか、国際社会、異文化理解をうながす講座もあります。一方日本研究講座では、社会、経済、ビジネス、政治をはじめ歴史、文学、芸術、思想・宗教など幅広い側面から日本を探求します。
海外からの外国人留学生と共に英語で学ぶ授業としてユニークなものであり、学問を通しての国際交流の場として日本人学生の積極的な参加を歓迎しています。
なお、本講座の履修単位の取り扱いは日吉学生部(大学院担当)窓口で確認してください。
レジデント・アシスタント(RA)について
国際センターでは、留学生といっしょに大学留学生用宿舎に住み、日々の生活を支援する日本人学生(レジデント・アシスタント(RA)と呼びます)を募集しています。RAは、日本にいながら留学生と交流できる貴重な経験をすることができます。
新しいことに挑戦したい方、国際的な経験・視野を広げたい方、組織作りに興味がある方、自分の体験を生かしたい方などは、応募を考えてみてください。
For Future Exchange Students
Student Exchange Program
The Graduate School of System Design and Management, Keio University (Keio SDM) welcomes international exchange students seeking to study at Keio SDM from our partner universities. Students need to be nominated by their home universities to attend our Student Exchange Program for one semester or one academic year beginning in either Spring or Fall Semester.
This section will outline the application procedures to become an SDM exchange student and provide other useful information.
Apply to be an Exchange Student
SDM staff will inform the student exchange program coordinators of our partner universities about the Application documents (including eligibility and requirements) and the application deadline.
Application Documents and procedures will be announced to the student exchange program coordinator of our partner universities.