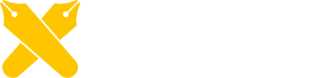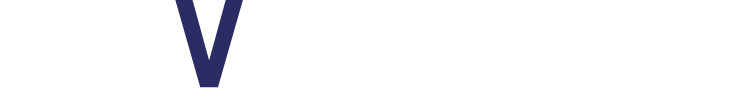研究科委員長メッセージ

目的を設定し、その実現を構想・実行する
多様な価値観が共存し、様々なものが繋がることで相互に作用している現代社会においては、その全体を静的なものとして捉えていくことはできません。実際、技術の進化は加速度的に早くなり、社会環境変化の激しさは増加しており、思いもよらなかったことが次々と起こっています。
このような状況においては、「そもそも何を目指すのか」を決めることも簡単ではありません。これまでの延長線上に目的を設定するのでよければ、目的設定は簡単です。しかしながら、技術進化により以前は出来なかったことが出来るようになってきました。また、社会環境の変化により、これまでとは違うところを目指すことも必要となってきました。つまり、次世代のリーダーは、目指すべき目的を設定する力、つまり「問いを立てる」能力が必要となっています。そして、実現不可能な目的設定をしても、それが実現できなければ価値がありません。あるべき社会を見据えながら、その実現の仕組みを考慮した上で、目的設定をしていくためには、仕組みをデザインする能力も同時に必要となります。
目的を実現するための仕組みをデザインするためには、全体を捉えるとともに、それを構成する部分とそれらの関係性を定義することが必要となります。そして、その仕組みを社会に実現していくためには、多様な関係者との合意形成や、進め方すらもデザインし、実行していくことが必要となります。つまり、これらをバラバラに扱うのではなく、統合的に扱うことが必要です。
多様性を活かす教育と研究の実践
慶應SDMでは、2008年の設立当初から、「目的設定」、「仕組みの設計」、「実現のためのマネジメント」を統合的に扱うための教育と研究をおこなってきました。それには「木を見て森を見る」ことが重要となります。そのために、多様な人たちとの協力により、多視点でものごとを捉えることや、多様な観点からの意見を活用し、統合することを目指しています。そして、これが、多様性を活かすための"横串の専門性"としての能力となります。
SDM研究科では、"横串の専門性"として複数の学問分野を横断するために、システムとデザインとマネジメントからなる独自の教育を提供し、分野横断的な研究を積極的におこなっています。幅広い年齢の方々が、世界各国から集まり、専門性が異なる多様な学生、研究員、そして教員が一緒に学び、より良い社会の実現に向けて議論しています。より良い社会の実現と、"横串の専門性"の習得を目指して、多様な人たちと一緒に学び、研究をしたいと考える皆さんの参加をお待ちしています。