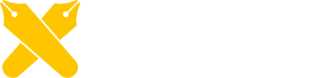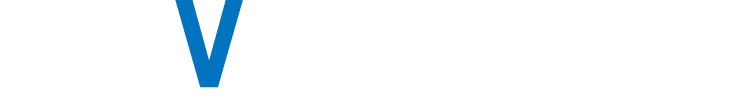国内連携
諸機関との連携
SDM研究科では、環境共生、安心・安全に代表される社会価値を考慮したシステムを実現するために、国内外の企業、研究機関、大学との活発な連携による教育・研究を行っています。また、企業等との連携を推進するために、システムデザイン・マネジメント研究所を設置しています。
国内における連携事業体・企業の例
東京大学、東京工業大学、東北大学、筑波大学、甲南大学、首都大学東京、学習院大学、安全工学会、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国際農林水産業研究センター、防衛省海上幕僚監部、防衛省技術研究本部、防衛省航空幕僚監部、 和歌山県、IHI運搬機械、アスカカンパニー、アディダスジャパン、アトナープ、NPO法人イノプレックス、インフラ・イノベーション研究所、NHKコンピューターサービス、NTTコムウェア、NTTデータ、 elephant design、小野測器、キヤノンマシナリー、コマツ製作所、SUMCO、サンブックス、 JR総合研究所、JFEエンジニアリング、住環境計画研究所、スズキ、スタンレー、 セガサミー、測位衛星技術、ソニー、千代田アドバンスト・ソリューションズ、 ツネイシホールディングス、THK、電力中央研究所、東京海上日動火災、東京海上日動リスクコンサルティング、 東京ガス、東京急行電鉄、東京証券取引所、東京電力、東芝、東芝エレベータ、東芝システムテクノロジー、東北電力、トヨタ自動車、豊田中央研究所、日揮、 日産自動車、日本IBM、日本経済新聞社、日本電気株式会社、日本有人宇宙システム、農林中央金庫、野村アグリプランニング&アドバイザリー、富士ゼロックス、吉田篤夫会計事務所、三井住友建設、三菱総合研究所、 三菱電機、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、村田機械、他