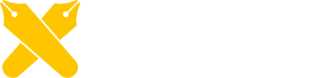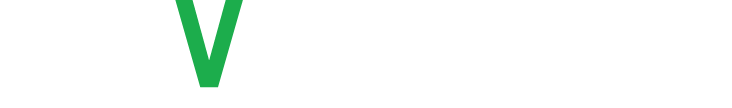SDM特別講義 2009年度 秋学期
| 講義日程 | 講師・演題 |
|---|---|
| 第1回 2009年10月2日 モデレータ教員: 当麻 |
 独立行政法人建築研究所 理事長 独立行政法人建築研究所 理事長SDM教授 村上周三 【演題】 住宅・建築・都市とエネルギーマネジメント(仮題) |
| 第2回 2009年10月9日 モデレータ教員: 当麻 |
 財団法人地球環境産業技術研究機構 副理事長・研究所長 財団法人地球環境産業技術研究機構 副理事長・研究所長茅陽一 【演題】 ポスト京都におけるエネルギーマネジメント(仮題) ■会場:日吉キャンパス独立館地下2階(DB201)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1934年生まれ。北海道出身。57年東京大学工学部電気工学科卒業、62年同大学院博士課程修了、工学博士。その後、講師、助教授を経て、78年東京大学電気工学科教授、95年に退官、東大名誉教授。同年より慶応義塾大学教授、98年より地球環境産業技術研究機構副理事長兼研究所長。専門はエネルギー環境システム工学。東京都科学技術功労者、環境省環境功労者。電気学会会長、エネルギー資源学会会長、政府資源エネルギー調査会会長等を歴任。現在、産業構造審議会地球環境小委員長、(独)科学技術振興機構原子力開発運営統括等を兼任。 <主な著書>『エネルギー新時代』(省エネルギーセンター、1987)、『地球時代の電気エネルギー』(日経サイエンス、1995)、『低炭素エコノミー 温暖化対策目標と国民負担』(日経新聞社、2008)他。 講義概要温室効果ガス排出抑制の中長期目標が盛んに議論されているが、エネルギーの低炭素化はその意味でも、また化石燃料という有限の資源制約に対応するためにも必然の方策である。そのための方策はいろいろあるが、鍵となるのは1)民生・運輸需要の電力化、2)発電の低炭素化、だろう。前者の実現には、住宅・建物における低温熱需要(冷暖房・給湯)に対してヒートポンプによる自然エネルギー利用の大幅拡大、プラグインハイブリッド車・電気自動車の大規模普及が前提となる。後者においては、第一に必要なのは原子力の更なる拡大だが、風力・太陽光発電などの自然エネルギー利用も当然の選択となる。ただ、これらは気象条件等による不規則な出力変動の調整にバッテリーの導入が必要で、安価なバッテリーの開発が急務となる。更に長期的視点からは、化石燃料を利用しつつCO2排出を抑制できるCO2回収貯留(CCS)技術の導入が有効であろう。いずれにせよエネルギーの低炭素化にはこれらを含んだ総合的アプローチが必要である。 |
| 第3回 2009年10月16日 モデレータ教員: 当麻 |
 東京工業大学 統合研究院 教授 東京工業大学 統合研究院 教授柏木孝夫 【演題】 新エネルギーの導入推進とそのマネジメント(仮題) ■会場:日吉キャンパス独立館地下2階(DB201) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1970年東京工業大学工学部生産機械工学科卒業、1975年同大学院博士課程中退。工学博士。米国商務省NBS招聘研究員(80〜81年)、東京工業大学工学部助教授(83〜88年)を経て、1988年東京農工大学工学部教授。1992年名古屋大学非常勤講師、1996年九州大学教授を併任。2000年東京農工大学大学院 評議員・図書館長、2007年より、東京工業大学統合研究院ソリューション研究機構教授(現職)。 講義概要政権が交代し、低炭素エネルギー社会へ向けた動きが加速されている。我が国は工業国家として、そのグランドデザインを明確に示す義務がある。電力に関して言えば原子力を始めとするメガインフラを基盤に、地産地消の新エネルギーシステムがスマート制御系を通してメガインフラと一体化し、自然エネルギーを最大限取り込めるシステムのモデルを構築することになる。2050年に向けた低炭素型エネルギーシステムの将来像を提示することにより、今後のイノベーションのあり方を論じる。 |
| 第4回 2009年10月23日 モデレータ教員: 当麻 |
 社団法人新エネルギー導入促進協議会 代表理事 社団法人新エネルギー導入促進協議会 代表理事石谷久 【演題】 低炭素型の交通システムとエネルギーマネジメント ■会場:日吉キャンパス独立館地下2階(DB201) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール昭和16年生まれ。昭和44年,東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博士課程修了。工学博士,東京大学宇宙航空研究所、同先端科学技術研究センター、同工学系大学院教授(地球システム工学専攻)、慶應義塾大学大学院政策・メデイア研究科教授)等を経て、平成21年から(社)新エネルギー導入促進協議会 代表理事。東京大学名誉教授.エネルギー資源学会会長。 文部科学省科学技術・学術審議会委員(資源調査分科会)、資源エネ庁総合エネルギー調査会委員(省エネ部会他)など歴任.現在経済産業省産業構造審議会委員、総合エネルギー調査会臨時委員,総合科学会議基本政策推進専門調査会専門委員など。 講義概要近年の温暖化防止のためのCO2排出抑制のつよい要請と,現在,ほとんど唯一の現実的な自動車燃料である石油資源(液体炭化水素)の価格高騰から従来の内燃機関自動車にかわる電動車両を中心とする次世代自動車の実現が期待されている.自家用乗用車によるCO2排出は先進国の家庭からの排出としてその比率が高く,また大気環境維持の点からもその対策は急務と考えられて久しいが,技術的な課題も多く従来,進展がほとんど見られなかったが,最近の急速な技術進歩とつよい社会的要請から電気自動車なども実用化への努力がすすめられている.その背景と技術的変遷,現在時点での実用化の課題,並びにその実現普及への政策などを紹介する。 |
| 第5回 2009年10月30日 モデレータ教員: 当麻 |
 株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長SDM教授 中上英俊 【演題】 世界の暮らしとエネルギー消費 ■会場:日吉キャンパス独立館地下2階(DB201) ■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール住環境計画研究所 代表取締役所長 東京工業大学特任教授 早稲田大学客員教授ほか 1945年岡山県生まれ。1968年横浜国立大学工学部建築学科卒業後、同大学大学院建築学専攻修士課程修了、東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程博士課程。1973年住環境計画研究所を創設し現在に至る。工学博士。 役職としては、日本エネルギー学会理事、ESCO推進協議会副会長。政府機関の委員としては、経済産業省総合資源エネルギー調査会委員として省エネルギー部会部会長、需給部会委員・新エネルギー部会委員、環境省中央環境審議会臨時委員として地球環境部会委員、総合政策・地球環境合同部会委員、国土交通省社会資本整備審議会臨時委員ほかを務める。 共著書に『エネルギー新時代―"ホロニック・パス"へ向けて』(省エネルギーセンター)、『地球温暖化問題ハンドブック』(アイピーシー)、『地球時代の環境政策』(ぎょうせい)など多数。 専門分野はエネルギー・地球環境問題、地域問題。 講義概要わが国の家庭用エネルギー需要は依然として増加基調にあり、地球温暖化防止に向けてエネルギー需要の増加を抑制し、さらに削減することが求められている。まず、われわれの暮らしとエネルギーの関わりの歴史を振り返ってみたい。また、将来の家庭でのエネルギー消費はどのような方向に向かうのかについてもシミュレーションモデルでの推計結果として示す予定である。 では、世界の家庭でのエネルギー消費はどのようになっているのだろうか?本講義では、欧米先進諸国におけるエネルギー消費とライフスタイル、住宅や所得水準等の状況をふまえながら紹介する。 さらに、これから爆発的なエネルギー消費の増加が見込まれる、アジアの途上国における家庭でのエネルギー消費の状況を解説する。 これらの結果から、わが国の家庭用エネルギーのあり方を考えると共に、アジア途上国に対するわが国の役割について考えてみたい。 |
| 第6回 2009年11月6日 モデレータ教員: 前野 |
 グーグル 名誉会長 グーグル 名誉会長村上憲郎 【演題】 Googleは、何をしようとしているのか? ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール2003年4月、Google Inc. 副社長兼 Google Japan 代表取締役社長として Google に入社以来、日本における Google の全業務の責任者を務めて来ましたが、2009年1月1日付けで退任し、名誉会長に就任しました。 Google 入社以前には、2001年に Docent の日本法人である Docent Japan を設立し、同社の社長としてe-ラーニング業界でリーダーシップを発揮しました。 1997年から1999年の間は、Northern Telecom Japan の社長兼最高経営責任者を務め、Northern Telecomに買収された Bay Networks の子会社である Bay Networks Japanとの合併を成功に導きました。後にNortel Networks Japanと改名された同社において、2001年中旬まで社長兼最高経営責任者を務めました。 日立電子株式会社のミニコンピュータシステムのエンジニアとしてキャリアをスタートした後、Digital Equipment Corporation(DEC)Japanのマーケティング担当取締役などを歴任し、マサチューセッツの DEC 本社にも5年勤務しました。 京都大学で工学士号を取得しています。 講義概要『世界の情報を整理して、世界中の人がアクセスできて、使えるようにする』というミッションを掲げて、次々と新しいサービスを、それも無料で提供するグーグル。ここ数年は、IT産業全体を根本的に変革するかもしれないといわれる『クラウド・コンピューティング』という新しいコンピューティング・スタイルの提唱者・推進者としても、注目されている。さらに、オバマ政権の『グリーン・ニューディール』政策に寄り添う形で、『再生可能エネルギー』や『スマートグリッド』へのコミットメントを深めている。講演では、この3点の個々の内容と、それらの相互連関の必然性と整合性を、概説する。 |
| 第7回 2009年11月13日 モデレータ教員: 狼 |
 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙利用ミッション本部 事業推進部長 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙利用ミッション本部 事業推進部長浜崎敬 【演題】 宇宙から地球の息づかいをみる-温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の概要- ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール宇宙航空研究開発機構(JAXA)温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)プロジェクトマネージャ。1954年生。77年東京大学工学部航空学科卒、79年同大学院修士課程修了。79年宇宙開発事業団(現JAXA)入社。システム計画部、衛星技術開発室、ワシントン駐在員事務所所長代理(宇宙ステーション計画NASA駐在員)、陸域観測技術衛星(ALOS)サブマネージャ等を経て、2003年より現職。主に衛星システム及び地球観測センサの研究、開発などに従事。国際宇宙航行連盟(IAF)技術委員。日本航空宇宙学会、日本リモートセンシング学会に所属。温室効果ガス観測、プロジェクトマネジメントなどに関する国内外での講演多数。 講義概要地球温暖化の現状、温室効果ガス観測の現状を概観するとともに、宇宙からの温室効果ガス観測の必要性と意義を述べる。また、2009年1月に打ち上げられた世界初の温室効果ガス観測専用衛星「いぶき」(GOSAT)の概要、観測原理と期待される成果を紹介する。 |
| 第8回 2009年11月27日 モデレータ教員: 小木 |
 ㈱東芝 研究開発センター 研究主幹 ㈱東芝 研究開発センター 研究主幹大富 浩一 【演題】 設計からデザインへ ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール㈱東芝 研究開発センター 研究主幹,工博。機械システム機器の開発,設計支援技術の研究・開発に従事。 日本機械学会(フェロー),日本計算工学会(副会長)。 講義概要Designは日本語では一般に設計と訳される。しかしながら、Designと設計のイメージはかなり異なる。このように、言葉の定義ができていないところに設計研究の進め方の難しさがある。そこで、Designを設計とデザインに分けて考え、ベースとしての設計、方向付けとしてデザインを事例を交えて紹介する。最後に、日本のものづくりの目指すべき方向を考える。 |
| 第9回 2009年12月4日 モデレータ教員: 西村 |
 兼松エレクトロニクス株式会社 第二ソリューション営業本部 エンジニアリングサポート部 マネージャー 兼松エレクトロニクス株式会社 第二ソリューション営業本部 エンジニアリングサポート部 マネージャー 宮崎元成 【演題】 日本のMONOZUKURIの神髄 ~自動車メーカーにおける製品開発力とコーポレートカルチャー~ ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール兼松エレクトロニクス株式会社にて、製造業における開発・設計業務の生産性向上に向けたPLMソリューション及びコンサルティングを担当。入社以来新規ビジネスの立ち上げに携わり営業部マネージャーを経て、現在エンジニアリングサポート部のマネージャーを務める。さまざまな製造業において設計・生産領域における多くのPLMプロジェクトを手掛る。神奈川大学経営学部卒。名古屋商科大学大学院マネジネメント研究科修士課程修了(MBA)。マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院エグゼクティブプログラム修了。自動車、自動車部品、電気、電子、精密機械など幅広い分野で設計・生産部門を中心に、コンカレントエンジニアリング、設計品質向上、ナレッジマネメントなどの革新を支援している。現場を重視し、人にはたらきかけて、じっくりと変革するコンサルティングに特徴がある。 講義概要日本のものづくりの強さとは何か。それは、持続的にものづくりを進歩させるための現場力や発想、それらを支える企業文化である。これまで、自動車メーカーにおけるデジタル開発を支援してきた経験から日本のものづくりの神髄をさぐる。 |
| 第10回 2009年12月11日 モデレータ教員: 高野 |
 文部科学省 科学技術政策研究所 第2研究グループ主任研究官 文部科学省 科学技術政策研究所 第2研究グループ主任研究官上野彰 【演題】 長い歴史を持つラボラトリーの組織的知識について ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール1987年北海道大学文学部卒、2003年東京大学大学院工学系研究科博士課程中退。この間公益法人シンクタンク勤務を経て、2001年内閣府原子力安全委員会事務局技術参与として原子力分野の組織文化の研究および安全文化醸成に取り組む。2004年、電力中央研究所社会経済研究所ヒューマンファクター研究センターにて組織診断の実践に取り組む。2006年より現職。現在は大学や公的研究機関を対象として、研究パフォーマンスと組織文化の関係、研究リーダーシップの在り方、また歴史的経緯や研究人材系譜の影響の研究に従事。さらに、欧米のトップクラス研究組織の組織文化等を調査している。 講義概要大正時代に財団法人として発足し、現在は独立行政法人である理化学研究所は、日本の科学技術の光陰を体現してきたといって過言ではありません。理研の90年余にわたる歴史の中では、科学界にインパクトを与える発明発見が成され、また社会の要望に応える製品開発に結びつく研究が重ねられてきました。本講義では、理研の中でも「最も理研らしい」と評される研究室を取り上げ、その展開を系譜学的に検討するとともに、そこから見えてくる「科学する組織の組織的知識とは何か」、について言及します。 |
| 第11回 2009年12月18日 モデレータ教員: 狼 |
 THK株式会社 代表取締役社長 THK株式会社 代表取締役社長寺町彰博 【演題】 THKの歩みと これからのTHK ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール最終学歴: 1974年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 主要職歴: 1974年4月 株式会社大隈鉄工所(現 オークマ株式会社) 入社 1975年10月 同 退社 1975年10月 THK株式会社 入社 1977年4月 同 甲府工場長 1982年3月 同 取締役 業務部長 1987年6月 同 常務取締役 管理本部長 1997年1月 同 代表取締役社長(現任) 1997年1月 大東製機株式会社(現 THKインテックス株式会社)代表取締役会長(現任) 1998年6月 株式会社ベルデックス(現 THKインテックス株式会社) 代表取締役会長(現任) 2007年5月 株式会社リズム 代表取締役会長(現任) 現在に至るその他: 2008年5月 社団法人日本工作機器工業会 会長 現在に至る |
| 第12回 2010年1月8日 モデレータ教員: 日比谷 |
 慶應義塾大学助教(医学部熱帯医学寄生虫学) 慶應義塾大学助教(医学部熱帯医学寄生虫学)慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員 齋藤智也 【演題】感染症対策と危機管理 ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィール慶應義塾大学医学部卒業。医学博士(慶應義塾大学・専攻:分子寄生虫学)、公衆衛生学修士(米国ジョンズ・ホプキンス大学、専攻:公衆衛生危機管理)。 2006年より文部科学省委託事業安全・安心科学技術プロジェクト研究統括補佐として、バイオテロ対策に関する情報収集、ワークショップやセミナー等を開催するほか、厚生労働科学研究班員として対バイオテロを中心とした対応指針作成、研究開発に従事。専門は公衆衛生危機管理(CBRNテロ、主に生物テロ)、バイオセキュリティ。 講義概要2001年の米国炭疽菌郵送テロ事件、2003年のSARS、そして今年は新型インフルエンザと、様々な感染症の危機が国際社会を揺るがしており、感染症対策は国家の安全保障の一部として見直されるべき問題となっている。 主にバイオテロ対策、そして新型インフルエンザ対策を事例として、その危機管理のあり方を考える。 |
| 第13回 2010年1月15日 モデレータ教員: 狼 |
 株式会社 eスター 代表取締役社長 株式会社 eスター 代表取締役社長赤澤輝行 【演題】 環境エンジン(排熱回収スターリングエンジン)の事業化を目指して ■会場:
■時間: 講師プロフィール1967年生まれ。1992年熊本大学工学部大学院修士課程卒業、パナソニック株式会社(旧名 松下電器産業)入社、空調研究所(当時)にて、空調用次世代コンプレッサの研究開発に従事、その後、パナソニック社内ベンチャー制度に応募し、株式会社eスターを起業。 これまで利用されずに捨てられている排熱からの電気などを取り出す環境にやさしいスターリングエンジン(環境エンジン)の開発を行い、事業化に取り組む。 講義概要19世紀初頭にスコットランドのロバート・スターリング牧師が発明し、 夢のエンジンと言われてきたスターリングエンジン。 これまで、さまざまな企業が事業化に取り組んできて、これまで、量産等の 事業化には、成功していない。 このスターリングエンジンを低炭素社会に貢献する環境エンジンとして、 弊社の事業化に向けた挑戦について、紹介する。 |
| 第14回 2010年1月29日 モデレータ教員: 小木 |
 日本SGI株式会社 産学官連携推進室 エグゼクティブ・コンサルタント 日本SGI株式会社 産学官連携推進室 エグゼクティブ・コンサルタント正田秀明 【演題】 スーパーコンピューター TOP500 その変遷を視る ■会場:日吉キャンパス協生館CDF室(C3S10)
■時間:19:00-20:30(6時限) 講師プロフィールスーパーコンピュータシステムの販売とその関連ビジネスに従事 近年は産学連携・シミュレーション分野の啓蒙活動に重点を置く 講義概要スーパーコンピューターの発展の経緯、特に日本に於けるここ10年の急激なユーザー・ベンダーの環境の変化とその要因につき「TOP500」ランキングから視える現象を述べ、併せ今後のあり方を考察する |