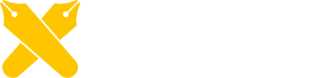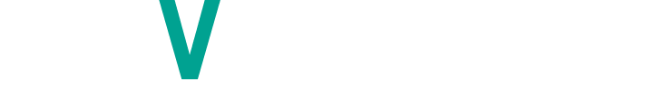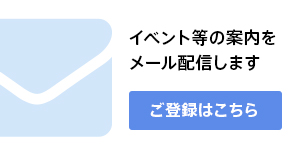| 題目 |
「慶應SDM公開講座 ソーシャルデザインと地域イノベーション」 |
|---|
| 日時 |
2014年9月2日(火)18:30-21:00(18:15開場予定) |
| 場所 |
慶應義塾大学日吉キャンパス独立館DB201【こちら】
|
|---|
| 講師 |
- 筧裕介 氏(issue+design 代表)
- 太刀川英輔 氏(予定)(NOSIGNER事務所 CEO/デザイナー)
- 渡邉さやか 氏(予定)(re:terra 代表理事 )
- 西村勇哉 氏(ミラツク 代表/慶應SDM非常勤講師)
- 前野隆司(SDM研究科委員長・教授)
|
|---|
| スケジュール・講座概要 |
2014年秋学期から慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科(慶應SDM)に「ソーシャルデザインと地域イノベーション」(講師:西村勇哉)が開講されます。
今回の公開講座は、授業開講に先立って、秋からの授業にゲスト講師として招聘する方々をお招きした特別セッションとして実施します。当日は、「ソーシャルデザインと地域イノベーション」を題材にゲストによるクロストークの他、来場された皆様によるショートダイアログの時間を設けます。
- 18:30-19:45
ゲストによるクロストーク①
参加者間のショートダイアログ
- 19:45-21:00
ゲストによるクロストーク②
参加者間のショートダイアログ
|
|
定員
|
200名
|
|---|
|
参加費
|
講演参加費は無料
|
|---|
|
申し込み
|
【こちら】のフォームからお申し込みください。
|
|---|
|
主催
|
システムデザインマネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所ソーシャルデザインセンター
|
|---|
|
お問い合わせ先
|
システムデザイン・マネジメント研究科
Phone : 045-564-2518
Email:sdm@info.keio.ac.jp
|
|---|
| ゲスト・プロフィール |
- 筧 裕介(かけい ゆうすけ)氏
issue+design 代表 http://issueplusdesign.jp/
東京大学大学院工学系研究科修了。東京大学大学院在学中より、社会課題をデザインで解決するソーシャルデザイン領域の研究、実践に取り組む。2008年issue+design設立。
共著書に、『地域を変えるデザイン』『震災のためにデザインは何が可能か』他。グッドデザイン賞、キッズデザイン賞審査委員長特別賞、日本計画行政学会・学会奨励賞、竹尾デザイン論評賞など受賞多数。
- 太刀川英輔(たちかわえいすけ)氏
NOSIGNER株式会社 http://nosigner.com
ソーシャルイノベーションデザインファーム NOSIGNER代表。社会に機能するデザインの創出(デザインの機能化)と、デザイン発想を体系化し普及させること(デザインの構造化)を目標として活動している。
平面、立体、空間を横断するデザインを得意とし、新領域の商品開発やコンセプトの設計、ブランディングを多数手がけ、数多くの国際賞を受賞する。
科学技術、教育、地場産業、新興国支援など、既存のデザイン領域を拡大する活動も。災害時に役立つデザインを共有する「OLIVE PROJECT」代表。IMPACT JAPAN fellow。University of Saint Jpseph (マカオ) 客員教授。
- 渡邉さやか(わたなべさやか)氏
一般社団法人re:terra http://www.reterra.org/
国際基督教大学アジア研究専攻。東京大学大学院「人間の安全保障」プログラム修了。
ビジネスを通じた社会課題の解決の必要性を感じ、2007年にIBMビジネスコンサルティングサービス(現IBM)に入社。新規事業策定や業務改善などのプロジェクトに携わりながら、社内で環境や社会に関する(Green&Beyond)コミュニティリードを経験、プロボノ事業立ち上げにも参画。また社外では、NPO法人soketを2010年設立、米国NPO法人コペルニクの日本支部立ち上げに従事。
2011年6月退職。現在、re:terra代表。IMPACT Japan東北復興ディレクター。NPO法人soket理事。被災地での産業活性プロジェクトや、(特に中小企業の)途上国・新興国進出支援、カンボジアでの事業立ち上げなど幅広く活動。
- 西村勇哉(にしむら ゆうや)氏
NPO法人ミラツク代表理事 http://emerging-future.org/
大阪大学大学院にて人間科学(Human Science)の修士を取得。人材育成企業、財団法人日本生産性本部を経て、2008年より開始したダイアログBARの活動を前身に2011年にNPO法人ミラツクを設立。
Emerging Future we already have(既に在る未来を手にする)をテーマに、社会起業家、企業、NPO、行政、大学など異なる立場の人たちが加わる、セクターを超えたソーシャルイノベーションのプラットフォームづくりに取り組む。
|